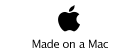子守唄を聞かせて
銭湯の湯舟の中で、カリンカはいきどおっていた。
「いきどおっていた」という言い方よりも、「怒っていた」と言ったほうが正しいかも知れない。何にせよ、カリンカは怒っていた。
(なによなによなによー! あたしが悪いんじゃないじゃん!)
元はと言えば、今日の夕食のおみそ汁に、くるみが具を入れ忘れたのがいけなかったのである。
それに気付いたカリンカは、例のごとく、くるみを罵倒した。
「やーい、まーた失敗してやんのー。くるみのばかばかばかばか・・・・」
「ばか」を連呼し始めた時点で、天城博士がカリンカに近付いたかと思うと、平手打ちを食わせたのだった。かわいた音が部屋に響き、いつものことだとあきらめていた仲人やサキ、くるみはあっけに取られた。
ほおを押さえてぼう然とするカリンカに、博士は激しく言った。
「いいかげんにしなさいっ! あんたとくるみのケンカは恒例行事だって言っても、その原因を最初に作るのは、カリンカ、あんたでしょう! 家の修理費だってバカにならないのに、毎日どこかに穴だの何だの開けられちゃ、たまったもんじゃないのよ! 風呂がまもダメにして、いったいどう言うつもり? 反省しなさいっ!」
研究所の風呂は、昔ながらの五右衛門風呂だ。その風呂がまを、カリンカの勘違いでダメにしてしまったのである。
風呂の外を偶然カリンカが通りかかると、誰かがお湯を使っている音がする。多分くるみだろうと思ったカリンカは、いたずら心をおこした。
保温のために少しだけつけられていた火に、マキをありったけくべると、火吹き竹で思いきり息を吹き込んだのである。
鋼鉄天使が吹き込む訳だから、並みの息ではない。たちまちマキに火が燃え移ると、風呂がまはモーレツに熱せられる。
「ぎぃあ〜〜〜〜っ!」
風呂から聞こえて来たのは、カリンカが期待していたくるみの声ではなかった。なんと仲人だったのである。
軽くはあったが、仲人の背中にやけどを負わせた上、風呂がまも、もしかしたら熱のおかげで穴が開いてしまったかも知れないと言うことで、風呂の修理がすむまで、四人は近所の銭湯を利用せざるを得ないことになってしまった。
帝国陸軍から、それなりに「鋼鉄天使研究」の名目でお金が出ているものの、その半分以上が家の修理費と食費に当てられてしまうので、博士が怒るのも当然の話である。
怒鳴られたカリンカは、数瞬の間だまっていたが、ちゃぶ台にはしと茶わんをたたき付けた。
そして、「お金!」と博士に言った。
「お風呂、行ってくる」
* * *
ぐしゃぐしゃと髪を洗い、乱暴に体を流して、再び湯舟につかったカリンカは、洗い場にいる女性たちを、見ることもなく見ていた。
東京の銭湯のお湯は熱い。大体45度くらいだから、足をつけると、ゆっくりと体を沈めなければならない。
そんな中に、遠慮会釈なくザハザバと湯舟に入っていったものだから、先に入っていた老齢の御婦人が、ぎろりとカリンカをにらみ付けたのだが、カリンカはそんな事には一向にかまっていなかった。
彼女は、いかにしてくるみをへこますかを考えるのに熱中していて、湯舟に人がいることなど、どうでもよかったのである。
「まったく、最近の娘は!」
御婦人が聞こえよがしに言って、出て行ったのにも気付かず、カリンカは湯舟に体を沈めているのだった。
そんな時、ガラガラと洗い場の引き戸が開いて、もう一人別の御婦人が入って来た。
年の頃四十五、六。長い髪を結い上げ、背筋をぴしりと伸ばして歩いて来るその姿は、美しくもあるが、どこかすごみさえ感じさせた。
おけを取って湯舟からお湯をすくい、さっと体にかけ終えた時、御婦人とカリンカの視線が交差した。
カリンカは、お互いの視線が交差した瞬間、火花が散ったような気がした。
(この女、出来る・・・・!)
カリンカがそう思ったのと同時に、御婦人は湯舟に体を沈めていた。ゆらゆらと波紋が広がり、カリンカの体に当たる。
「お姐さん、ゆらさないでよ。お湯が食いつくから」
カリンカにしてみれば、言ってみたい台詞ではあった。銭湯に通い始めた時、粋なふうのお姐さんが、同じ台詞を言ったのを聞いて、カリンカは「かっこいい!」と思っていたのだった。
「おや」
御婦人が、視線をカリンカに投げた。
「これくらいでお湯が食いつくたあ、ずい分とヤワなお肌なんだねぇ」
切れの良い江戸弁が、御婦人の口をついて出た。その口調で嫌みを言われたのだから、たまらない。
人以上に勝ち気なカリンカは、腹が立っているのも手伝って、御婦人に言い返してしまった。
「そ、若いんだから、食いついて当たり前よ。そっちは食いつかれすぎて、少しも感じてないんでしょ。年は取りたくないわねー」
その台詞を聞き終えた瞬間、御婦人は目と口を丸くしてしまっていた。そして、するどい目付きでカリンカをにらんだ。
カリンカも御婦人をにらみ返した。意地の張り合いである。
(先に湯舟を出たら、負けるわ) 二人ともそう思っていた。
そして、お湯は相変わらず、熱いままであった。
* * *
「さあさあ、お風呂に行きましょ」
天城博士が、両手を打ちながら言った。気まずい空気の流れていた部屋が、少しだけその沈黙から晴れたように、くるみとサキ、仲人は思った。
秋も中ほどの、下町の銭湯への道を、四人はそぞろ歩いた。家々の軒先に、秋桜のはちが置かれていた。
「まあ、かわいいお花」
サキが秋桜を見て言った。
「わあ、ほんとうですぅ。まるでサキちゃんみたいなお花ですぅ」
くるみが言うと、サキはぽっと顔を赤らめた。
(姉さん・・・。明日、このお花の種を買ってこなくちゃ。そして来年の秋、お庭をお花でいっぱいにするの・・・・。姉さん、喜ぶわ)
「ねー、ご主人さまぁ。明日、このお花の種を買いにいくですぅ。そしてお花で、お庭をいっぱいにするですぅ」
くるみの言葉に、サキは顔をさらに明るくした。
(姉さん! 同じことを考えているなんて、私と姉さんの心は、やっぱりひとつだったのね。私、姉さんを好きでいてよかった・・・!)
くるみはくるみで、こんなことを思っていた。
(来年、このお花でお庭がいっぱいになったら、ご主人さまはくるみの髪に、『ほら、くるみ。きれいだよ』って言って、お花をかざってくれるんですぅ。そして、やさしくやさしく口づけしてくれるんですぅ。きゅい〜ん!)
ほおを赤くして体をくねらせるくるみとサキを、仲人と天城博士はあきれつつながめていた。
「ほら、寒くなってくるから、早く行くわよ」
すたすたと歩いて行く博士を見て、仲人はくるみとサキに言った。
「ほ、ほら、二人とも。置いてかれちゃうよ」
歩きながら、天城博士もあることを思い出していた。
(そう言えば、あのひとがこの花を私にプレゼントしてくれたことがあったわね)
「あのひと」とは、言うまでもなく綾小路博士のことである。照れながら秋桜の花たばを渡してくれた綾小路博士の顔を、天城博士ははっきりと憶えている。
(ふふっ、気取っちゃって・・・。でも、うれしかったわね。だって、今でも好きなんですもの)
くすくす思い出し笑いをする博士を見て、仲人は困惑した。
「きょ、今日は三人ともどうしちゃったんだろう?」
そうこうするうち、四つ角を右に曲がれば銭湯の玄関が見えてくると言う所まで、四人が歩いてきたところで、女学生風の二人連れとすれ違った時、サキは二人の会話を聞きのがしてはいなかった。
「なーんだか二人とも恐かったわねー」
「そーよね。鬼みたいな顔して、にらみあってんの」
「そりゃあそうよ、あんな熱いお湯につかってんだから、鬼になって当然よ」
「寒いからさ、あったまろうと思っても、入れないもんねー」
嫌な予感がした。サキは、前を行く三人を呼び止めた。
「何だか・・・嫌な感じがします」
「嫌な・・・感じ?」 天城博士がサキに聞く。
「そう・・・すごく・・・」
「だーいじょうぶですぅ!」
くるみが大声を上げた。
「カリンカちゃんはいいコですぅ。あんなかわいい妹が、変なことするはず、ないです。ねー、ご主人さま?」
平静を装ってはいても、大きい声を出すと言うことは、くるみもまた不安なのだ。聞かれた仲人も、ただ生返事を返すしかなかった。
到着した銭湯の玄関先で、やはり今来たとおぼしき二人の男が、何事か話をしている。
「今かかあが湯から帰って来て、『たいへんなことンなってる』ッてんで、飛んで来たんだ」
「おうおう、俺も聞いてきて、飛んで来たッてとこだ。なァ、金髪碧眼のチビとお竜さんが、我慢比べで勝負してるって言うじゃねえか」
「何だか面白そうだなァ。でも女湯だから入れねェなァ」
「どうだい、番台のババァに『金二倍払うから、勝負の様子を見届けさせろ』って言ってみるか」
「冗談じゃねェ。かかあに知れたら、大変なことになるぜ」
「お互い、扱いづれえ女をもらって、困ったもんだよな」
「そうだそうだ。ああ言うのはずうずうしいから、一生家にいるかも知れねえ」
二人は大笑いして、銭湯の中へ入って行った。
「金髪碧眼」・・・・・どう考えてみても、カリンカ以外の人物は思い浮かばない。四人はそろって、顔にタテ線が入ってしまったのだった。
「どうしよう・・・」
仲人が情けない声を出した。
「どうしようもないわね」
意を決した天城博士が答えると、くるみとサキのほうを向いて、続けた。
「こうなったら、強行突破ね。行くわよ」
「はいっ!」
「あ、あの、僕は?」
仲人が言うと、博士は言った。
「すぐすむから、お風呂入ってて」
「えー?! やーですやーですぅ! ご主人さまもいっしょに、キョーコートッパするですぅ!」
くるみが大声で抗議した。あわてて仲人は、くるみをいさめた。
「だめだよ、くるみちゃん! 温泉の露天風呂じゃないんだから」
「ぶー。ご主人さまとくるみは、一心同体ですぅ。二人の愛の力があれば、どんなつらいことでも、乗りこえられるですぅ」
おろおろしながら、サキも口を出してくる。
「姉さん、仲人さんも言ってることだし、ほんの少しだけ我慢して下さい」
あとを受けて、仲人が続けた。
「くるみちゃん。聞き分けのないくるみちゃんなんて、くるみちゃんじゃないよ」
少し強く言ったその一言に、くるみはしおしおとなってしまった。
「はい・・・わかったですぅ」
「ね、ちゃんと外で待ってるから、サキちゃんと博士とで、がんばってくるんだよ」
「はいですぅ! ご主人さまの御期待、しっかりと受け止めたですぅ!」
どうなることかとハラハラしていた天城博士は、ほっと胸をなで下ろした。そして、くるみとサキに目配せして、先頭に立って銭湯の中に入って行こうとして、引き返した。仲人は再び困惑した。
「ど、どうしたんですか?!」
「お金渡すの忘れたわ。はい、ゆっくり入っててね」
手のひらでお金を受け取りながら、仲人は気持ちの上で足ゴケしてしまっていた。
強行突破などと大層なことを言ったものの、下手に突撃して行くと、カリンカがどんな態度を取るかわからないので、結局はいつもどおりに、番台にお金を払って入ることになった。番台には、いつものおばちゃんではなく、銭湯の主人が座っている。
「おう、らっしゃい」
「あら? いつものおばちゃんじゃないのね」
博士が言うと、主人が顔をしかめた。
「今日はちょっとなぁ。女湯で勝負してるッてんで、かかあの野郎『あたしが見届けるから、あんた番台やっとくれよ』って、中に飛び込んじまいやがってね。物好きなかかあで困るよ」
「はあ・・・」
「まァ、もう治まってるみたいだから、ゆっくり入ってってくんねェ」
「どうも・・・あ、三人分払っとくわね」
のれんをくぐって脱衣場に入ってみると、用意してある木のベンチに、一人の女が寝かされて、ウンウンうなっている。その女に向かって、いつもの番台のおばちゃんが、うちわで風を送っていた。
「まったくあんたって人は、小さいころから見てるけど、相変わらず強情だねェ。いい加減その強情を直したらどうだい。ンなこったから、いつまでたってもいいひとが見つかんないんだよ! ェえ?」
「余計なお世話よォ・・・ちくしょォ、も一回勝負させとくれよォ。あたしゃ我慢比べで負けたこたァねェんだよ・・・。あのチビィ・・・・」
「おやめよおやめよ! やめときなよォ。ェえ? お湯ゥうめろって言ってくンのはわかるけど、あのコは反対に『わかせ』って言ってんだよ。あんなのに勝てるわけ、ないじゃないか」
この寝かされている女が、件のお竜さんのようだ。会話を聞いていたくるみが、心配そうに博士に言う。
「は、はかせぇ・・・。どうしたらいいですか? カリンカちゃん、大変なことしちゃったみたいですぅ・・・」
サキは言葉も出せなくなっている。二人に向けて、天城博士は言った。
「いい? 気を大きく持つのよ。いざとなったら、二人で合体して、カリンカを押さえ付けなさい。行くわよ」
鋼鉄天使の力が、一般人に使われたとすると、カリンカは言わずもがな、博士はおろか、くるみやサキまで軍法会議にかけられて、この世から抹殺されることも覚悟しなければならない。
服を脱いだ三人は、もうもうと湯気の立ちこめる洗い場へと、歩みを進めて行った。
引き戸を開けると、出口を探していたかのように、白い湯気がもわもわとあふれ出して来た。天城博士が、奥の壁に描かれている富士山の絵を確認しようとしたが、それさえ見ることが出来ないくらいの湯気が、洗い場にたちこめているのだ。
洗い場の一番奥に湯舟があり、男湯との仕切り壁と左側の壁に各々五つ、真ん中の背の低い仕切りの両側に各々三つのカランが準備されているという、東京でも最新の設備を備えた銭湯だ。奥の壁には、富士山に帆掛け船の、美しいペンキ絵が描かれている。
床は松の板ばりだったのを、衛生上の理由から水色と白のタイルばりとし、さらには壁側のカランのそれぞれに、大きな鏡を取り付けたというから、思いきった投資がなされている銭湯である。このような改装にふみ切ったおかげで、ご近所の常連はもちろん、わざわざ遠くから入浴しに来るお客までいる。新しもの好きの江戸っ子の心をばっちりつかんだおかげで、この銭湯は大繁盛というわけだ。名前もそれまでの「松の湯」から、「衛生湯」と変えている。
「松の湯」のころから、我慢比べがあることはあった。男湯に入りに来る職人同士で行われるくらいのものだったが、まさか女湯で我慢比べが行われるとは、主人もおばちゃんも思いもよらなかったことだろう。
前述通り、東京の銭湯のお湯は熱い。一分以上入っていることが出来ないくらいである。その中にカリンカとお竜さんが入っていて、結局はお竜さんが負けたのだ。
(いったいどんな体をしてるのかしら。鋼鉄天使の耐熱温度も、研究項目に加えておくべきだったわ)
歩みを進めながら、天城博士は思った。
「♪おっふろー、おっふろー、おっきいおっふろー。おっきいおっふろがだいすきでっすぅー」
風呂おけをくるくる回しながら、くるみはうきうき状態である。出雲行きの途中途中で泊まった旅館の風呂が大きかったのが、よほど印象に残っていたらしく、東京に帰ってからすぐ、研究所の風呂を大きくしろと、駄々をこねていたほどだ。
「姉さん、本当に銭湯が大好きなのね」
サキが言う。くるみが後を受けて続けた。
「だーいすきですぅ。ご主人さまも、サキちゃんも、博士も、カリンカちゃんもいっしょに入れるから、とーってもだーいすきですぅー」
くるみの言葉を聞いて、サキは再び顔を赤らめながら、思った。
(ああ、姉さん・・・。このくらい大きなお風呂を作ってあげられたらいいな・・・。そして、姉さんと二人だけでお風呂に入るの。シャボン玉遊びをしたり、体を流しっこしたりして・・・。楽しいだろうな・・・)
くるみのほうはと言うと、またもやこんな考えをめぐらしていた。
(ご主人さまとの愛の巣には、こーのくらい大きいお風呂を作るです。そうして、ご主人さまと流しっこしたり、湯舟で泳いだりして遊ぶんですぅ。きっととぉーっても楽しいですぅ。きゅい〜ん!)
引き戸のあたりでもじもじしている二人を見て、博士は再びあきれていた。
「また何か変な事考えてるわね・・・。ほらほら、二人とも! 他にも入る人がいるんだから、そんな所に立ってないで! 風邪ひいちゃうわよ!」
我を忘れていた二人は、湯舟のかたわらにいた博士の言葉に気がつくと、そばまでかけ寄って来た。そして、サキがおけで湯舟からお湯をすくい、体にかけようとしたその時である。
「こりゃあ!」
突然かん高い声が、洗い場に響いた。
「えっ? 何?」
驚いたサキが、おけを取り落とす。ろれつの回らないさっきの声が、再び聞こえた。
「お湯をゆりゃすにゃあ! 食いついてくりゅう!」
サキはおびえて、くるみの影にかくれた。
「いったい何なの?」
博士が湯舟の奥に人影があることを確認すると同時に、声はこんなことを言った。
「湯舟名主のこのあたしの、お許しを得てかりゃ、お湯をくめーい!」
「えっ、なになに? 何ですか?」
半分面白がっているくるみが、湯舟に近づき、じっと目をこらして「湯舟名主」を名のる人物を見た。すると「湯舟名主」もくるみに近づいて、誰かを確認しようとした。そのとたんである。
「あーっ! カリンカちゃんですぅ!」
くるみが大声で叫んで、「湯舟名主」を指差した。
「ああっ! くるみお姉ちゃん!」
カリンカは湯舟から立ち上がった。熱いお湯につかり過ぎて、体はゆでだこのように真っ赤である。
ふらふらしながら、カリンカは両の手を腰に当てて、「へっへーん!」と叫び、胸をはった。目もうつろな状態である。
「カリンカちゃん、だーいしょうりー! がまんくりゃべの女王、湯舟名主のカリンカしゃまとお呼びー!」
再びそう叫んでみせると、右手でVサインを作り、三人の前に突き出した。
くるみ、サキ、天城博士は目を丸くして、あっけに取られたままでカリンカを見つめた。
「やっと・・・やっとこりぇでくりゅみに勝てりゅじょお〜・・・。くぅりゅぅみぃ〜・・・・いじゃ尋常にしょ・・・お・・・ぶぅ・・・」
だんだん声が細くなって、カリンカの体はあおむけに湯舟の中へ倒れこんでしまった。
「カリンカ!」
「カリンカちゃんっ!」
三人の叫ぶ声が聞こえたか聞こえずか、カリンカはぶくぶくと湯舟の底に沈んで行くのだった。
* * *
ずきずきとした頭の痛みに気付いて、カリンカが体を起こしてみると、あたりは黒一色の空間だった。
「え? ここ、どこぉ? あたし、お風呂屋さんにいたはずよね・・・」
少しよろけて、カリンカは立ち上がる。からだがふらつくのは、お風呂につかり過ぎたせいだと思った。
黒一色とは言っても、足はしっかりと空間をとらえているので、とにかくカリンカは歩いてみることにした。
「いったいどこなのかなー? 博士ぇー! くるみお姉ちゃーん! サキお姉ちゃーん! 仲人さーん!」
名前を呼んでも、ただこだまとして返ってくるだけである。その時、ずっと先のほうに、ぼおっとした光が見えた。
「あそこね!」
カリンカは走り出した。100メートルを5秒以下で走る鋼鉄天使の脚力をもってすれば、その光までにはものの数分でたどり着けるはずだった。
しかし、カリンカはたどり着けなかった。光が間近に迫ったその時、彼女の左側から、何か異様に大きなものが近づき、彼女の体をはじき飛ばしてしまったのである。
あざやかな受け身で、カリンカは再び立ち上がった。
「なによ! くるみ? サキお姉ちゃん? 戦うんなら正々堂々勝負しなさいよ!」
そう言ったとたん、カリンカは足元をすくわれ、空間にたたき付けられた。そして、かなり上のほうへ持ち上げられたかと思うと、再び下のほうへ、まるでゴムまりのように体を何度も落とされる。
以前くるみと、京都の寺で戦った時の、あの恐怖がまざまざと思い出された。
「何で・・・何で? あたしが一番強いはずなのに・・・!」
ぐったりと空間に体を横たえるカリンカの耳に、重く太い男の声が聞こえた。
「ふがいないな、カリンカ」
「あ・・・まさか!」
「思い出したかね・・・」
「ワルスキー博士! いったい・・・どうして!」
「いつまでくるみごときに手こずっておるのだ。最強の鋼鉄天使として、恥ずかしくないのかね?」
カリンカは何も言えなかった。そして、体を起こすと力を振りしぼり、声のする方向へ走り出し、何度も拳をくり出したが、まるで固い壁を打つかのごとく、効果はなかった。
ワルスキー博士の声が、再び聞こえた。
「ふふふ・・・。茶番ついでに面白いものを見せてやろう」
カリンカの右手の方向に、ぼおっとした光が見えてきた。先ほどの光の正体はこれだったのである。そして、カリンカは驚愕した。
そこには巨大な手に握られた、一人の少年の姿があった。
「ミハエル・・・さま・・・?」
「そうだ。お前の主人だ。ぶざまだろう」
ワルスキー博士の声が聞こえた。
「ご主人さまを離せ!」
カリンカが叫ぶと同時に、ミハエルを握る手が動き、さらに強く握った。
「ぐあああっ!」
ミハエルの断末魔が響く。
「ミハエルさまぁーっ!」
再び叫ぶカリンカに、ミハエルは息もたえだえに言った。
「カリンカ・・・僕のことはいい・・・・早く・・・・逃げて・・・」
「いやだ! ご主人さま! あたしのご主人さま!」
カリンカは泣き叫んだ。
「茶番も茶番、大茶番だな・・・。もういい。そうしたら、きさまも同じ運命にあわせてやろう」
ワルスキー博士の声が響いたとたん、カリンカの体も、巨大な手に握られていた。
「ちくしょう! 離せ! 離してよ!」
首以外の体全部が握られているので、もがこうにももがけない。手はゆっくりと力をこめ始めた。
「ああああっ!」
カリンカの骨が、ぎしぎしときしみだした。追い打ちをかけるようにワルスキー博士の声が言った。
「あの世で仲良く暮らすがいい・・・さらばだ! ミハエル、カリンカ!」
「いやああああああっ!」
* * *
カリンカは、布団から身を起こしている自分に気付いた。息は荒く、全身から汗がしたたり、寝巻きや敷布を濡らしている。
もう一度まわりを見渡すと、そこは黒い空間ではなく、いつもの研究所の座敷だ。あけられたふすまの向こうの部屋に、くるみ、サキ、仲人の三人が眠っているのが見えた。
「・・・リンカ! カリンカ! 大丈夫?」
ようやく聞こえた声のほうを見ると、天城博士が心配そうにカリンカを見つめている。
「あ・・・・博士!」
カリンカは博士に抱きついていた。体が小きざみに震え、涙があふれ出た。
「う・・・あぅ・・・・」
「夢を見たのね。大丈夫よ、私がついているから」
「恐かった・・・恐かったよ・・・・」
カリンカの背中を、天城博士はやさしくたたいた。そして、汗に濡れた寝巻きを新しいものに着替えさせ、自分の寝床にカリンカをまねき入れた。
一人用の布団に二人入るのだから、お互いの体を密着させて、ようやく納まった。
「ね、寒くない?」
博士が声をかけると、カリンカはこくんとうなづいた。
その時ふいに、カリンカは甘いにおいをかいだ気がした。なにかの花の香りのような、そんなにおいだった。
カリンカは、博士からさっきのように怒られるのだろうと思っていた。だが、博士はカリンカの背中に腕を回して、やさしく抱きとめているだけだった。博士の温かな体温が、自分の全てを包んでいてくれているかのように、カリンカは感じた。
「ね、カリンカ」
ふいに博士から声をかけられて、カリンカは首を上に向け、博士の顔を見た。やさしい笑顔が、そこにあった。
「みんなあなたの事が好きよ。だから、あまり心配させないでね」
「・・・・」
カリンカは体をきゅっと固くした。そして、やっと聞こえるような声で、博士に聞いた。
「博士」
「なあに?」
「あたし、かわいい?」
「かわいくない女の子なんて、いないわよ」
「ほんと?」
「ほんとよ」
カリンカはしばらく黙っていたが、突然博士の体に腕を回した。
「どうしたの? 寒いの?」
困惑した博士が言うと、カリンカは少しためらったような表情をしてみせながら、こう言いはじめた。
「やっぱり・・・あたしって、ダメなコなのかな」
博士の体に回した腕に力がこもる。
「だって・・・だってあたし、いつもお姉ちゃんたちとケンカしてばっかりだし、仲人さんにも博士にも迷惑かけっぱなしだし・・・」
再びカリンカの体が震え出した。嗚咽をこらえながら、カリンカは続けた。
「あたし・・・もっとかわいい女の子になりたい。素敵な女の子になりたい。そうしたら、みんなに迷惑かけなくてすむもん・・・。ね、博士、教えて。どうしたらかわいくなれるの? どうしたら素敵な子って言われるようになるの?・・・教えて・・・・!」
聞きながら天城博士は、アカデミーの殺りくマシーンとして誕生させられた、カリンカの運命を呪った。そして、カリンカの髪を指ですきながら、言った。
「わかった。じゃあ教えてあげるわね。カリンカにも大切な人がいるでしょう?」
「うん・・・」
「その大切な人のことを、ずっと心の中で想い続けること。それが素敵な女の子になれる、秘密のおまじないよ」
「それって・・・」
「恋をすること。女の子の必須条件よ」
博士の言葉に、カリンカは思わず博士の顔を見ていた。やさしく微笑む博士の顔は、今だ知らぬ母の顔をカリンカに連想させるのに、必要十分な要素を満たしていた。そして、さっきかいだ甘いにおいが、再びカリンカの鼻をくすぐっていた。
暖かな博士の体温が、カリンカの心をいやしていくのを、カリンカ自身も、はっきりと感じ取っていた。ただ、それと同時に、言い知れぬ不安が彼女を襲い続けていたのは、間違いのない事実だった。
アカデミーでの生活は、申し分なかった。世界を征服することが、ワルスキー博士を中心としたアカデミー上層部の最大の目的である。それに応えることが、カリンカの存在意義であり、そうでなければならないと思い、思わせたのも、ミハエルの存在であった。
もしかしたら、と、カリンカは思った。あたしは、ミハエルさまのために生きているのではないか。
だが、アカデミー上層部は、くるみたちとの闘いの途中で、ミハエル共々姿をくらましてしまった。そのことを知った時、カリンカは冷静に振る舞おうと思い、事実そのようにした。こころの奥底にある「弱さ」を悟られたくなくて、はしゃいでみたり、くるみやサキ、博士に突っかかってみたりした。
そんな彼女も、仲人には、ほんの少しだけ心を開くこともあったが、あくまでもミハエルだけが、カリンカの心のよりどころなのであった。
今、この生活の中に、ミハエルがいれば、どんなに楽しいだろうと、カリンカは思った。
そう思った瞬間、カリンカは自分が「恋に落ちている」と感じた。疑う余地はない。もうカリンカは、ミハエルなしでは生きていられないことに、気付かされたのであった。
しかし、ミハエルはどこにいるかも、生きているのかも知れない人間となってしまった。そう思うと、不安がつのるのも無理はない話である。カリンカは、天城博士にしがみつき、こらえきれない涙を流すまいと、必死で耐えた。その時である。
カリンカの耳に、今まで聞いたことのない歌が聞こえてきた。
ねんねんころりよ おころりよ
カリンカよいこだ ねんねしな
やさしく、慈悲にあふれた歌。カリンカは顔を上げて、博士の顔を見た。目を閉じ、カリンカの背を軽く手のひらでたたきながら、博士は続けて歌った。
里のみやげに 何もろた
でんでんだいこに しょうのふえ
カリンカの目から、涙があふれ出た。止められなかった。
嗚咽をあげながら、カリンカは泣いた。こんなに泣いたのは、生まれて初めてだった。博士や自分の寝巻きが、涙でぬれるのもかまわず、カリンカは泣いた。
その嗚咽を聞きながら、博士は子守唄をくり返し歌った。やがて嗚咽が寝息に変わり、博士もまた、夢の世界へと落ちて行くのだった。
* * *
カーテンのすき間から、うっすらと光がもれているのに、一番最初に気が付いたのは、カリンカであった。
「う・・・・」
寝ぼけまなこを手の甲でごしごしこすり、カリンカは寝床からその光の方を見つめていたが、起き上がらねばならないような衝動にかられた。
体にからんでいた天城博士の腕をそっとはずし、起こさないように寝床から出て立ち上がると、カリンカはカーテンを開けた。
そこには、見慣れた裏庭の風景が広がっている。サキが苗を買ってきて植えた花々が、そこを色どっていた。
カリンカは、そんな風景を何も考えず、ただながめていた事に、たった今気付いた。そして、ガラス戸を開くと、ひんやりとした秋の真新しい空気を吸った。
その瞬間、カリンカの中で何かが新しくなっていくのを、彼女は強く感ぜずにいられなかった。
カリンカは居間へ走り、そこにすえつけてあったラジオを抱え、そばの戸だなに入っていた延長コードを見つけだすと、再び床の間に戻った。そして、ラジオを裏庭に置き、そのコードに延長コードをつなぐと、床の間のコンセントにプラグをつないだ。
彼女の右手がラジオのスイッチを兼ねた音量つまみを、回しきるまで回した。ラジオのきょう体が真空管で暖まり、ゆっくりと音がスピーカーから流れ出してきた。それは指導員の声であった。
『ラジオ体操第一! よーい!』
すぐに軽やかなピアノの音が出て、あとは指導員のかけ声に合わせて体を動かせばいい。カリンカの額に、汗が光り出すのに、たいした時間はかからなかった。
開きっぱなしのガラス戸から、部屋で寝ていた四人が、何事かと裏庭をのぞいていた。その四人に向け、カリンカは満面の笑みを浮かべると、こう呼びかけた。
「みんなおはよう! いっしょに体操しようよ! 気持ちいいよ!」
眠い目をこすりながら様子を見ていたくるみは、カリンカの一言を聞くと、残りの三人に向かって言った。
「なんだか面白そうですぅ。ご主人さま、サキちゃん、博士、カリンカちゃんといっしょに体操するですぅ!」
そして、くるみはサンダルをつっかけると、カリンカの左横に立ち、いっしょに体を動かしはじめる。
「姉さん、私もいっしょにやります!」
「僕も!」
サキと仲人も、ぞうりやサンダルをはいて、くるみの隣へ一列に並ぶと、ラジオに合わせて体操を始めた。やがて天城博士も合流し、カリンカの右横に立って体を動かした。
博士がふとカリンカのほうを向くと、カリンカも博士のほうを向いていた。そして、カリンカは博士にウインクをしてみせると、その笑顔を空に向けて体操を続けながら思った。
(ミハエルさま、あたし、元気でいるよ! そして、いつか会えたら、あたしの一番いい笑顔で、ミハエルさまを迎えてあげるんだ!!)
秋の太陽がゆっくりと登り、青い空が見えた。その空に向かって、カリンカは号令をかけた。
「いっちに、さんっしっ!」
「ごーろっく、しっちはっち!」
あとの四人が呼応すると、さらに大きな声でカリンカは号令をかけながら思った。
(声よ、届いて! ミハエルさまに聞こえるように!)
そして青空は、高く高く澄み渡るのだった。
おしまい