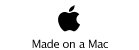アントニオ・カルロス・ジョビンの「波」をBGMに・・・
「ふあ・・・・」
瞬は、思わず大あくびをした。
日曜のお昼時、明るい日差しのさすリビングの、ふかふかのソファに座っていると、眠気をもよおすのも仕方のないことかもしれない。
(たいくつ・・・・)
そばにあったクッションを胸に抱くと、瞬はさほど面白くもない番組を流していたテレビを、リモコンで消した。
(なんか楽しいことないかな・・・・)
日差しがやさしく、瞬を心地よい眠りに誘う。うつら、うつらしていると、突然、
「こらっ! 瞬!」
「は、はいっっ!」 瞬は思わず飛び上がってしまった。
声のしたほうに顔を向けると、そこに氷河がくすくす笑いながら立っていた。
「もお・・・何ぃ、氷河?」
氷河はほほえみながら言った。
「そんなふうにしてると、お前ってまるでテディ・ベアだぜ」
「ぼく、そんなに太ってないよ!」
抱いていたクッションをほおると、氷河はそれを受け止め、元の場所に戻した。
「ずいぶん御退屈な御様子で・・・」
「だってさ、兄さんは映画に行っちゃうし、紫龍は春麗と買い物に行ってるし、星矢は美穂ちゃんとデートに行っちゃったし・・・」
「それで俺とお前が残ったってワケだ」
氷河はくるりと背中を向けた。
「俺がすごい計画を持ってるぞ」
「なに? それ」
「海を見に行こうぜ」
「海?」
氷河は瞬の方に向き直った。
「そ、いい考えだろ」
「まさか泳ごうって言うんじゃないの?」
「いくら俺だって、4月から泳ごうって変な考えは持ってないさ。ただ海を見に行くだけだよ」
別に大切な用があるワケでなし、瞬は氷河に同意した。
「氷河ぁ・・・」
「ん〜、なんだあ?」
「これ、恥ずかしいよ・・・」
「別にいいじゃないの」
瞬が恥ずかしがるのも、無理はない。一応少年っぽい格好をしてきた彼ではあったが、氷河のスタイルときたら、Tシャツにジーンズ、ゴムぞうり、頭には麦わら帽子、首にはタオルと、まるっきり海の家のオヤジという感じだ。しかも、そば屋の出前に使うようなごつい自転車に、二人乗りしているのである。
「その格好、誰から教わったのさ・・・」
「ん〜、辰巳のヤツに海に行くって言ったら、こーゆー格好しろって言われたんだ」
「辰巳さんったら・・・」
辰巳のセンスに、がっくりと肩を落とす。その言葉を真に受ける氷河も氷河だった。道行く女子高生が、二人を見てくすくす笑う。瞬は氷河にしがみついた。
「氷河ぁ・・・早く行こうよ・・・」
地方小都市にある城戸家の屋敷は、高台に位置することもあって、その街のどこからでも確認することができる。それほど大きな家なのだが、その姿がようやく見えてくる場所が、二人の着いた海水浴場である。
「ふぅ〜っ、やっと着いたぁ〜」
氷河は、額に流れる汗をぬぐった。
「ね、氷河、砂浜に行こうよ」
にこにこして瞬が言うが、氷河は答えない。海を見つめたままだ。
「どうしたの?」
「こおってない!」
「へ?」
「俺、凍ってない海を見るの、久しぶりなんだよ!」
自転車のカギもそこそこに、氷河は海岸へかけだした。
「あ、待ってよ、氷河!」
あわてて自転車のカギをかけると、瞬は氷河の後をおいかけた。
「うっははーいっ!!」
大声を上げながら、氷河は波打ち際へと走っていったが、もんどりうって倒れこみ、ぐしょぬれになった。
「ぷはぁ〜っ」
氷河は頭をぶるぶる振った。水滴が細かく散っていく。
「大丈夫?」
瞬は手を差しのべた。
「あ、ごめん」
瞬の手を取り、氷河は立ち上がろうとしたが、バランスをくずして、瞬を海へ引っぱり込んでしまった。
互いにびしょぬれの二人は、しばらく見つめあっていたが、どちらともなく笑い出していた。
「あ、あははは、いやだな氷河ったら、ぬれちゃってるよ」
「お前だってびしょぬれじゃないか、わはははは」
瞬は突然立ち上がり、走り出した。
「あ、待て、瞬!」
「やーい、ここまでおいでーだ!」
氷河も立ち上がり、水をバシャバシャ言わせ、瞬の後を追った。
ひとしきり走って、二人は自転車の置いてある場所へ戻った。
瞬は、持ってきたデイパックの中から、トランジスタラジオを取り出し、スイッチを入れて、適当にダイヤルを合わせた。
とたんにファンキースタイルのジャズが流れ出し、やがて終わった。DJがしゃべり出す。
『はい、キャノンボール・アダレイの「マーシー・マーシー・マーシー」でした。次の曲は・・・』
そこまで聞いていて、瞬は氷河に話しかけられた気がして、彼の方を向いた。
「何? 氷河」
「え? 別に何も・・・」
「そう?」
瞬は再び海を見つめた。DJが続ける。
『・・・と言うことで、このかたのリクエスト。アントニオ・カルロス・ジョビンの「波」です』
乾いたギターのイントロが始まった。その時である。
(うふふ・・・うふふ・・・)
瞬の耳に、誰かの声が聞こえてきた。もう一度、氷河の方を向く。氷河は、不思議そうな顔で、瞬を見つめた。
(ね、わらってよ・・・すてきなえがお、ぼくらにみせて・・・・・)
氷河の他には誰もいないし、後はラジオと波の音が聞こえるだけだった。
(きっと、波の精の声かもしれないな・・・) そんなふうに、瞬は思った。
「瞬」
呼び掛けられて、瞬は氷河のほうに振り向くと、氷河は瞬のほおに、キスをした。「波」と波の音がシンクロして、心地よい気分になる。瞬は氷河に言った。
「氷河、今日は楽しかったね」
「ん、あ、そうだな」 そう言って、氷河はちょっと照れた顔をした。
「さあ、もう帰ろうか」 氷河が言った。
「今度自転車こぐの、お前だぞ、瞬」
「え〜、やだよぉ」
「ぜーたく言わないの。さあ、俺乗るぜ」
氷河は荷台に座り、瞬を手招いた。
「もう、しょうがないなあ」 そう言っても、瞬はほほ笑んでいる。
「それじゃ、出発!」
瞬は自転車をこいだ。二人の耳に、低く、そして高く、波の音が聞こえてきた。
おしまい