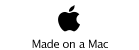愛の塩焼き
東京は下町の、秋の夕暮れである。
天城博士の「鋼鉄天使研究所」・・・とは名ばかりの民家の中庭で、一人の少年が夕飯の準備をはじめた。
少年の名は、神維 仲人と言う。家人と交代で食事当番をしている仲人は、今日のおかずにサンマの塩焼きを作ることにした。現在のように、ガスレンジなどという便利なものがない時代である。七輪の火でサンマを焼くのである。
かたわらには、塩をたっぷりとふってあるサンマが、焼きあみにはさまれて、焼かれるのを待っている。
「そろそろいいかな」
仲人は、木炭の火が真っ赤におこっているのを確かめると、焼きあみを七輪に乗せた。そこをさらにうちわであおぐと、炎が焼きあみの上までのぼってくる。
「ごしゅじんさまぁー! ごしゅじんさまぁー!」
そう言いながら仲人の元にかけ寄って来たのは、鋼鉄天使壱号機、くるみである。
ひょんなことから、仲人を「ご主人さま」と慕う彼女である。
「あ、くるみちゃん」
「ご主人さま、なにしてるですか?」
「うん、今日のおかずを作ってるんだよ」
「お魚さんを焼くですね。こんなことくらい、くるみがやるですぅ」
「あ、あ、でもね、これには少しコツがあるんだよ」
「コツ・・・ですかぁ?」
仲人には、分かり過ぎるくらい分かっている事を、くるみにうまく説明するには、大変な時間がかかる。
そこが仲人には難しいから、少しちゅうちょしてしまうのだ。
くるみは、体型からして、一見成熟しているようだが、仲人のくちづけで目覚めさせられるまで、冬眠状態であったと言ってもよい。そんな少女に、世の中のいろいろな事象を説明してあげるというのは、まさに至難のわざである。
「コツ・・・そうだなあ、お魚さんは、ちょっとコゲてもいいけど、コガしすぎたらいけないんだよ」
「コゲるって、どういうことですかぁ?」
「うーん・・・」
仲人は頭をかかえた。ちょっと考えた後、仲人はくるみに向かって言った。
「そうだ、くるみちゃん、いっしょにサンマを焼こうよ」
その言葉を聞いたとたん、くるみは気色ばんだ。
「きゅい〜ん!」
そして、仲人に抱きついた。
「ご主人さまとお魚さんを焼けるなんて、くるみ、幸せですぅ」
豊かな胸が、仲人の顔に押し付けられる。仲人はいつものセリフを口にせざるを得なかった。
「く、くるみちゃん、苦しいよぉ・・・」
空はすっかり、あかね色に染まっていた。その中をカラスが数羽飛んで行った。そして、その空に向かって、サンマを焼く煙がのぼっていった。
「♪ごっしゅじんさまっとー、いっしょにー、おっさかなさんを、やくでっすぅー」
適当な節をつけて、くるみは歌いながら、七輪へ向けてうちわで風を送った。かたわらには仲人がいて、サンマの焼け具合を注視している。香ばしいにおいがただよった。
パチパチと木炭がはじけ、炎があみの上までのぼる。盛大に出る煙が、ゆるりと吹きはじめた風に乗って、仲人のほうへ向いだした。
「こほん、こほんっ」
少し煙を吸った仲人は、思わずむせてセキをした。
「ああっ、ご主人さま、大丈夫ですか?」
くるみが心配になって聞く。
「う、うん、大丈夫だよ。それよりも、あみをひっくり返そうよ」
「はいっ、わかったですぅ」
くるみがあみを返すと、実にいい色でサンマは焼けていた。それを見て、くるみは感激した。
「うっわぁ、おいしそうですぅ」
「そうだね、くるみちゃん、上手にできたよ」
「きゅい〜ん! ご主人さまにほめられて、くるみ、うれしいですぅ! くるみ、片側もがんばって焼くですぅ」
全身で喜びながら、くるみはまた七輪に向かい、風をうちわで送った。その姿を見ながら、仲人はとても幸せな心持ちになる自分を、嬉しく思った。
くるみは、いつも通りのメイド服を着ていた。ふと仲人は、くるみが時々和服を着ることを思い出した。
天城博士の外出でお供をする時、くるみとサキは和服に着替えることが多い。もっとも時代が時代であるから、女性の洋服姿と言うのは、めずらしい部類に入る。
そんな中、天城博士とカリンカの洋服の着こなし方は、まさしく「モダン・ガール」、通称「モガ」そのものである。
特にカリンカの洋服姿は「可憐」だと、仲人は思っている。
あとの二人、くるみとサキは、和服がよく似合った。サキの和服姿は「清楚」、くるみのそれは「優美」だと、仲人は感じていた。
(今日はお供じゃなかったんだっけ・・・)
博士のお供も当番制である。今日はカリンカがお供役であった。和服姿のくるみを見られなくて、仲人は少し残念に思った。
考えてみれば、こんなに女性を意識している自分を、仲人は想像だにしていなかった。
兄の神人との協同生活では、きびしい神道の修行が主であり、愛だの恋だのは御法度であった。それが今では、四人の女性に囲まれて暮らしているのだから、意識するなと言われても無理である。
ただ、一線だけは超えるまいと、ひたすらに祈る自分は、陰陽道宗家・神維家の人間なのだと、仲人は強烈に感ぜずにいられなかった。
くるみが慕ってくれる、それだけでいいと、仲人は思うのだった。ほんの少しだけの恋慕、「かわいいな」とか「きれいだな」くらいは許されてもいいと、仲人は考えている。
「・・・じんさまぁ! ごしゅじんさまぁ!」
くるみの声で、仲人はふと我に返った。自分の目の前に、くるみの顔が最接近している。
「ご主人さま、どうしたですか? お腹でも痛いですか?」
「えっ、あ、いや、そのっ・・・」
顔が赤くなる。なんだかくるみに見透かされたような気になって、仲人は横を向いてしまった。
「な、何でもないよ」
「顔が赤いですぅ。お熱があるですか?」
くるみの顔が再び接近して、彼女と仲人のおでこが合わさった。仲人は少し照れてしまった。
「・・・・・」
「うーん、お熱はないようですぅ」
「・・・あ、いけない! サンマがコゲちゃうよ!」
「いけないですぅ!」
くるみがあわてて、あみを七輪から下ろすと、寸での所でサンマはコゲ過ぎるところであった。ほっと二人は胸をなで下ろした。
「助かったぁ〜。これで失敗したら、今日のおかずは、みそ汁とつけものだけだったよ」
「本当に良かったですぅ。あ、それと、もう一つ良かったことがあったですぅ」
「な、何?」
「ご主人さまといっしょにサンマが焼けて、くるみ、うれしいですぅ。これもご主人さまとくるみの、愛の協同作業。新婚気分ですぅ」
くるみの目は、ハート形の様相を呈している。少しあきれつつも、仲人は嬉しかった。
「姉さん! 仲人さん!」
サキの声が聞こえた。二人を呼びに来たようだ。
「あ、サキちゃんですぅ」
「おみそ汁ができましたよ。仲人さん、お魚は焼けていますか?」
「あ、うん、サキちゃん、今日はくるみちゃんもいっしょに焼いてくれたんだよ」
「まあ・・・・。姉さんが焼いたお魚が食べられて、私、幸せです」
ぽっと顔を赤らめるサキを見て、くるみはニコニコとほほ笑んだ。
「やっぱりサキちゃんはかわいいですぅ。さー、ご主人さま、みんなでいっしょにごはんにするですぅ!」
居間のほうに目をやると、天城博士とカリンカがちゃぶ台に着いていた。カリンカはお茶わんをはしでチンチンたたきながら言った。
「うー、お姉ちゃんたちー、早くしてよぉー。お腹ペコペコだよぉー」
「ほら、カリンカ、お行儀悪いわよ」
博士は、白い湯気のたつ、ぴかぴか光るごはんを、お茶わんによそい始めていた。
(やっぱり、僕って幸せなのかな?)
仲人はそう思っていた。
おしまい